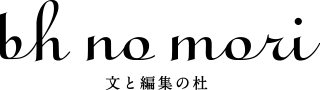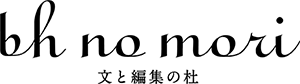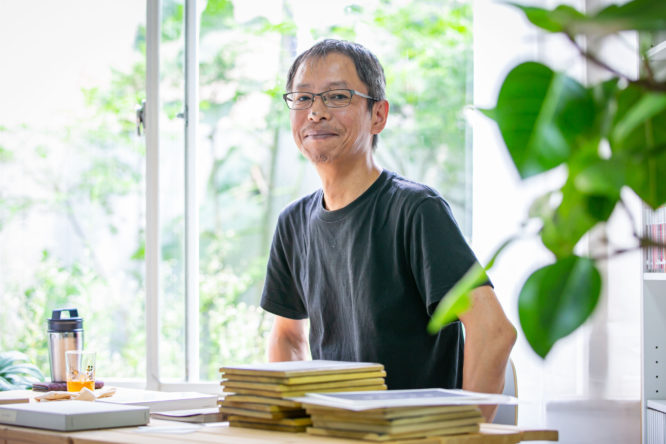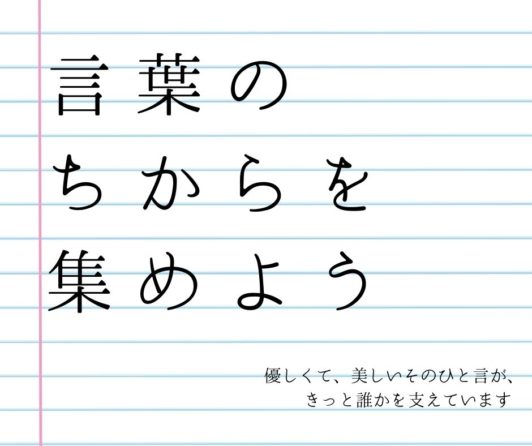column
コラム本は面白いか、面白くないかだけじゃない。二人の編集者が営む小さな本屋 hoka books 嶋田翔伍さん、西尾圭悟さん

堀川五条の大きな交差点のほど近く。一本の細い路地に入ると、景色が変わる。連なる低い軒、古い格子のガラス戸、無造作に置かれた消火バケツ。長屋が向かい合うその一角に“hoka books”は店を構える。運営するのは、ともに編集者として活躍する嶋田翔伍さんと西尾圭悟さん。大学時代に映画サークルで出会った二人はそれぞれの活動を経て、2021年6月にこの小さな本屋をオープンした。
似ているようで違う、違うようで似ている二人
 子どもの頃から小説や漫画が大好きだった、と笑顔を交えながら話す嶋田さん。ハキハキと率直な話し方はアクティブな印象だ。編集業の傍らイベント企画や動画撮影など幅広い活動を続けてきたが、あくまで「中心は本と決めている」と言う。2019年には一人出版社「烽火書房(ほうかしょぼう)」を立ち上げ、本作りに励む日々を送る。
子どもの頃から小説や漫画が大好きだった、と笑顔を交えながら話す嶋田さん。ハキハキと率直な話し方はアクティブな印象だ。編集業の傍らイベント企画や動画撮影など幅広い活動を続けてきたが、あくまで「中心は本と決めている」と言う。2019年には一人出版社「烽火書房(ほうかしょぼう)」を立ち上げ、本作りに励む日々を送る。
初出版の書籍『Go to Togo 一着の服を旅してつくる』は、日本とトーゴを行き来する著者・中須俊治氏の活動を綴ったエッセイ。「日本編=縦書き」「トーゴ編=横書き(逆さま)」が交互に構成されているという見たことのない体裁。読者は本をひっくり返しながら読み進めることになるのだが、そのうち、“価値観が回転する”という著者の体験が理解できる、という仕掛けだ。

落ち着いた声のせいだろうか。嶋田さんが“動”だとすると、西尾さんは“静”の雰囲気。大学・大学院と建築を専攻し、学生時代から雑誌や映画などのメディア制作に携わってきた。現在は編集者として主に建築関係の出版物を手がけながら、展示会やワークショップの運営を行うなど、こちらも活動内容はさまざまだ。
「建築も本もメディアの一つ。建築と本づくりって近いものがあると思うんです」。たくさんのパーツを組み立て、いろいろな人が制作に関わり、それを第三者が体感し行動につなげていく。その点でも建築と本は似ているのだと西尾さんは言う。「メディアというものをなるべく線引きせずに考えることもできるんじゃないかな」
二人がこの店を立ち上げた目的は少し異なっている。「僕は自分で出版社をやっているので、逆に作り手じゃない側から本に携わってみたいと思ったんです」と一貫して本にこだわる嶋田さん。対して西尾さんにとって「本屋」はメディアの一つ。「いろんな広がりを得たいなっていうなかで、この本屋も作っているんです」。本、そして編集に携わっている点も、その活動が多岐に渡っている点も似ているのに、考えていることは面白いほど違う。それでいて、どことなく同じ姿勢を感じるのはなぜなのだろう。二人の話を聞いていると、そんな疑問が浮かんできた。
キーワードは「作り手の顔が見える本」

売り場に並ぶ本も色とりどり、というか一見バラバラだ。好きなジャンルじゃなくてもこの広さならひと通り見てもらえるからと、あえてジャンルで分けずに陳列する。とは言え、当然ながらここに並ぶ本には二人が決めた基準がある。選書時に着目するのは、その本の特異性。とくに作られた過程の特別さを大切にしている。「作っている人の顔やストーリーが見える感じ」と西尾さんは表現する。
なかでも嶋田さんの印象に残っているのは、詩人の今唯ケンタロウ氏による『レチエ』というファンタジー小説。著者自ら一冊ずつ手製本しているところに惹かれて仕入れを決めた。「すごく手間のかかっている造本が綺麗で。実際その綺麗さだけで買っていく人もいるほどです」。取材時には売り切れていて手にとることはできなかったが、嶋田さんの話を聞くだけで作り手に対する興味がわいてくる。「大事に作った本なんやなっていう感じがすれば。どっちかというと、作り手びいきなのかもしれないですね」
本にはいろいろな要素がある。表紙のデザインも、言葉遣いや紙の種類などさまざまな要素が重なり合ってできている。編集者として制作に携わるとき、「その随所に作り手の感性が宿っていく」のを感じるのだと西尾さん。「きっとその感性にビビッとくる人がいる。読まなくても受け取れるものが、本にはあるんじゃないかな」。
「本って、別に面白くなくてもいいんかなと思うんです」。そう、嶋田さんは言葉を続けた。「理解できなくてもいいし、内容がささらなくてもいい。面白くなくても読んだ意味はあるし、その体験が無駄になることはない。本って、◯か☓かの二択じゃないと思うんですよね」
たとえ面白いと思えなくても、もしかして読まなかったとしても、受け取れる何かが本にはある。今まで知らなかった本との付き合い方を教えてもらった気がする。小さなこの本屋は、自由に広がる本の世界につながっているのだ。
(取材・文 遠藤道子)